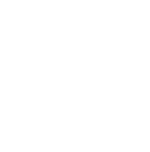MOVIE
LATEST MOVIECLOSE
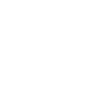
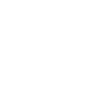


永代製作所は、グッドイヤーウェルテッド製法を主軸にした革靴をはじめ、革製品の企画デザイン、パターン、製造まで一貫しておこなう、設立から4年目の革小物製品の製造メーカー。居を構えるのは、グリーンの外観が印象的な文京区白山通りに面した3F建てビル。1Fには裁断機(クリッカー)やラスター、圧着機などの大型機械が並び、2Fは底周りの作業場、3Fが事務所兼、縫製、型紙を引く場となっており、それぞれのフロアを荷物用エレベーターが行き来することで場と場をつないでいる。
ここでは、3人の職人が型紙設計から縫製、底付けとそれぞれの分野のスペシャリストとして靴づくりのすべての工程を担う。代表の宮澤さんは大手靴メーカーの技術科で14年間務めあげ、年間400〜500足ものパターン設計に携わってきた経緯を持つ型紙師。関さんはミシン縫製、石橋さんは底付けと、3人ともに同僚として、それぞれの工程で技術を活かしたものづくりをおこなっている。
永代製作所でつくられる靴について型紙を引く宮澤さんは「靴はあくまで工業製品。工業製品であるということに必要性を感じている。100足作れば、そのすべてが同じクオリティーを保持していなければならない。つくったモノに責任を負うということ。1足になるまでの作業効率を重視し、どこまで無駄を省いて良いモノをつくれるかを基準に型紙を引いています」と話す。
1足の靴ができあがるまでには、幾つもの工程があり、靴づくりには、原形となる木型(ラスト)の存在が欠かせない。木型に合わせて革を切り出すための型紙(パターン)を引き、革を裁断、パーツとなる革同士を張り合わせた際の段差を一定に保つために漉き加工を施し、専用ミシンで革を縫い合わせていく。ここまででようやく革靴らしい形(アッパー)が見えてくる。
そして、”釣り込み”の工程へ。釣り込みには、ヒトの手でおこなう”手釣り”と、ラスターと呼ばれる機械でおこなう機械式の2通りの方法がある。ハンドメイドを生業にしている職人はもちろん手釣りでおこなうが、量産ベースで考えた場合は、断然、機械式の方が効率や一定の品質を保つ面でも優れている。
釣り込みを終えると、いよいよ靴らしくなってくる底周りの工程へと進む。靴底の材料はベンズと呼ばれる、牛革の中でも特に繊維が固く引き締まっている部位を使う。専用の接着剤を塗り圧着機にかけ、出し縫いを経てヒール付け、コバ(革の切り口)を整え、仕上げに靴磨きをおこなってやっと完成するのだ。
一般的に手縫い(ハンドソーン)靴というのは、木型に釣り込まれたアッパーと靴底を、ヒトの手で縫い合わせていくモノを指す。機械でおこなうか、ヒトの手でおこなうかの違いであるが、どちらが良いというコトではなく、どれだけ気概をもって臨んでいるか、職人の心意気ひとつなのだ。
同社が得意とするのは、オリジナルの永代式グッドイヤーウェルテッド製法(フレキシブルグッドイヤーウェルテッド製法)。最大の魅力はその屈曲性にある。足全体が包み込まれているような感覚があり、従来のグッドイヤーウェルテッド製法で作られた靴とは一線を画す履き心地を与えてくれる。
その開発に至るまでには技術の上にあるもう一つ上の技術・創造力が鍵となった。日々新たな製法を模索していく中で生み出され、機械式で手製靴のクオリティーを表現してみせたのだ。まさに、機械式とハンドメイドのハイブリッド製法といえるだろう。
また、こだわりは一見わからないところにも表れている。スラックスを履いた時の見え方のバランスを考慮した履き口の広さは、これまでに幾通りの型紙(パターン)を引いてきたことで養われたバランス感覚に他ならない。
会社を立ち上げたことによって、「いままで当たり前だと思っていたことが、すべて自分たちでおこなわなければならなくなった。もちろん大変な思いもするが、細かな部分にも目を配れるようになった。製作所とつけているのは、靴もやるが、鞄も財布もやるということ」と、自分たちで会社を立ち上げた理由を語る。
「永代」という名称は、宮澤さんの父の会社名に由来。また、オリジナルとして展開するブランド名も「EVERLASTING」。「EVER(〜永久に続く)」、「LAST(靴の木型)」とも掛け合わせてネーミングしたそうだ。父とは異なる道へと進んだが、想いを胸に、未来へと永く続くブランドに成長させていく気持ちが込められている。今後さまざまな革製品を取り扱う予定。思いつくままに製作を楽しんでいる。